このページでは夏目漱石の吾輩は猫である 第一章(1)をWebアプリらくらく読書プレーヤーを使って読書できます。
この続きは 吾輩は猫である 第一章(2) 夏目 漱石でご覧いただけます。らくらく読書プレーヤーを使うと縦書き・横書きをいつでも切り替え可能で文字スクロール機能(テキストアドベンチャーやビジュアルノベルゲームのように1文字ずつ流れるように表示する機能)や全ての漢字にルビを表示できる機能などで読書が苦手な方でもすらすらと読み進めることができます。
らくらく読書プレーヤーについての詳細と操作方法については トップページ または操作方法説明ページ をご覧ください。
らくらく読書プレーヤーの基本的な操作方法(説明)
各行ごとの表示の終わりを示す ▽マーク
 が表示された状態の時に画面上をタップ(クリック)すると
次の行の表示(文字スクロール)に移ります。各ページの最後の行が表示された後にタップすると次のページの表示が切り代わります。
が表示された状態の時に画面上をタップ(クリック)すると
次の行の表示(文字スクロール)に移ります。各ページの最後の行が表示された後にタップすると次のページの表示が切り代わります。また各ページの途中の行の表示中であっても[←1ページ戻る][1ページ進む→]のボタン
![[←1ページ戻る][1ページ進む→]ボタンと[現在のページ番号/最終ページ番号]の表示](https://easyreading.web.fc2.com/novel/images/BookReader_1PageModoru_1PageSusumu.png) をタップすることでページをいつでも切り替えることも可能です。
をタップすることでページをいつでも切り替えることも可能です。[←1ページ戻る]と[1ページ進む→]の2つのボタンの間に表示されている数字は[現在のページ番号/最終ページ番号] を意味しています。
[△ボタン表示](上向きの三角形のボタン)
 というボタンをタップすると
というボタンをタップすると文字スクロールの速度の指定 や ルビの振り方(全ての漢字にルビを振る、全く表示しない) などの各種設定ができる設定ウィンドウ


を表示する[設定ボタン]、 現在のページ番号と日付時刻を一緒に記録できる栞(しおり)ブックマークウィンドウを表示する[栞ブックマークボタン]、 1,5,10,50ページ単位でページを進めたり戻したりできる各ページジャンプボタンを表示する[ページジャンプボタン]
![[設定ボタン][ブックマークボタン][ページジャンプボタン]](https://easyreading.web.fc2.com/novel/images/BookReader_Button_Setting_BookMark_PageJump.png) を表示することができます。
を表示することができます。[▽ボタン非表示]と書かれているボタンをタップすると再度
[←1ページ戻る] [現在のページ番号/最終ページ番号] [1ページ進む→] [△ボタン表示]
という表示状態に戻すことができます。
なお、このページが開かれてから数十秒~1,2分以上待っても以下の画像(夏目漱石の吾輩は猫である 第一章(1)の場合)のようにプレーヤーが起動されない場合 (表題や作者名、はじめ(1ページ)から読む 等のボタン類が表示されない場合)、 プレーヤーの読み込みが不完全の可能性がありますのでお手数ですが正常に起動するまで何度かブラウザの再読み込み(リロード)を行ってください。
(* なお らくらく読書プレーヤーの起動にはJavaScriptが必要です。)
以下の画像は 夏目漱石の吾輩は猫である 第一章(1) の らくらく読書プレーヤーでの各ページのスクリーンショット画像(縦書き・タテ方向表示 すべての漢字にルビ表示) です。


どこで生(うま)れたかとんと見当(けんとう)がつかぬ。何(なん)でも薄暗(うすぐら)いじめじめした所(ところ)でニャーニャー泣(な)いていた事(こと)だけは記憶(きおく)している。吾輩(わがはい)はここで始(はじ)めて人間(にんげん)というものを見(み)た。しかもあとで聞(き)くとそれは書生(しょせい)という人間(にんげん)中(じゅう)で一番(いちばん)獰悪(どうあく)な種族(しゅぞく)であったそうだ。この書生(しょせい)というのは時々(ときどき)我々(われわれ)を捕(つかま)えて煮(に)て食(く)うという話(はなし)である。
*書生とは 他人の家に世話になって家事を手伝いながら勉学する者。


この書生(しょせい)の掌(てのひら)の裏(うち)でしばらくはよい心持(こころもち)に坐(すわ)っておったが、しばらくすると非常(ひじょう)な速力(そくりょく)で運転(うんてん)し始(はじ)めた。書生(しょせい)が動(うご)くのか自分(じぶん)だけが動(うご)くのか分(わか)らないが無暗(むやみ)に眼(め)が廻(まわ)る。胸(むね)が悪(わる)くなる。到底(とうてい)助(たす)からないと思(おも)っていると、どさりと音(おと)がして眼(め)から火(ひ)が出(で)た。

ふと気(き)が付(つ)いて見(み)ると書生(しょせい)はいない。たくさんおった兄弟(きょうだい)が一疋(ぴき)も見(み)えぬ。肝心(かんじん)の母親(ははおや)さえ姿(すがた)を隠(かく)してしまった。その上(うえ)今(いま)までの所(ところ)とは違(ちが)って無暗(むやみ)に明(あか)るい。眼(め)を明(あ)いていられぬくらいだ。はてな何(なん)でも容子(ようす)がおかしいと、のそのそ這(は)い出(だ)して見(み)ると非常(ひじょう)に痛(いた)い。吾輩(わがはい)は藁(わら)の上(うえ)から急(きゅう)に笹原(ささはら)の中(なか)へ棄(す)てられたのである。









吾輩(わがはい)がこの家(いえ)へ住(す)み込(こ)んだ当時(とうじ)は、主人(しゅじん)以外(いがい)のものにははなはだ不(ふ)人望(じんぼう)であった。どこへ行(い)っても跳(は)ね付(つ)けられて相手(あいて)にしてくれ手(て)がなかった。いかに珍重(ちんちょう)されなかったかは、今日(こんにち)に至(いた)るまで名前(なまえ)さえつけてくれないのでも分(わか)る。吾輩(わがはい)は仕方(しかた)がないから、出来得(できう)る限(かぎ)り吾輩(わがはい)を入(い)れてくれた主人(しゅじん)の傍(そば)にいる事(こと)をつとめた。



吾輩(わがはい)は人間(にんげん)と同居(どうきょ)して彼等(かれら)を観察(かんさつ)すればするほど、彼等(かれら)は我儘(わがまま)なものだと断言(だんげん)せざるを得(え)ないようになった。ことに吾輩(わがはい)が時々(ときどき)同衾(どうきん)する小供(こども)のごときに至(いた)っては言語同断(ごんごどうだん)である。自分(じぶん)の勝手(かって)な時(とき)は人(ひと)を逆(さか)さにしたり、頭(あたま)へ袋(ふくろ)をかぶせたり、抛(ほう)り出(だ)したり、 へっつい の中(なか)へ押(お)し込(こ)んだりする。



*代言とは 弁護士の旧称。法廷などで依頼人に代わって、その言い分を述べること。

我儘(わがまま)で思(おも)い出(だ)したからちょっと吾輩(わがはい)の家(いえ)の主人(しゅじん)がこの我儘(わがまま)で失敗(しっぱい)した話(はなし)をしよう。元来(がんらい)この主人(しゅじん)は何(なん)といって人(ひと)に勝(すぐ)れて出来(でき)る事(こと)もないが、何(なに)にでもよく手(て)を出(だ)したがる。
吾輩は猫である
『吾輩は猫である』(わがはいはねこである)は、夏目漱石の長編小説であり、処女小説である。1905年(明治38年)1月、『ホトトギス』にて発表されたのだが、好評を博したため、翌1906年(明治39年)8月まで継続した。 上、1906年10月刊、中、1906年11月刊、下、1907年5月刊。
「吾輩は猫である。名前はまだ無い。どこで生れたかとんと見当がつかぬ。」という書き出しで始まり、中学校の英語教師である珍野苦沙弥の家に飼われている猫である「吾輩」の視点から、珍野一家や、そこに集う彼の友人や門下の書生たち、「太平の逸民」(第二話、第三話)の人間模様が風刺的・戯作的に描かれている。
着想は、E.T.A.ホフマンの長編小説『牡猫ムルの人生観』だと考えられている。 また『吾輩は猫である』の構成は、『トリストラム・シャンディ』の影響とも考えられている。
あらすじ
吾輩は猫である 第一章(1)「吾輩」の最初の記憶は、「薄暗いじめじめした所でニャーニャー泣いていた」ことである。出生の場所は当人の記憶にはない(とんと見当がつかぬ)。その後まもなく書生に拾われ、書生が顔の真ん中から煙を吹いていたものがタバコであることをのちに知る。書生の掌の上で運ばれ(移動には何を利用したかは不明)、笹原に我輩だけ遺棄される。その後大きな池の前~何となく人間臭い所~竹垣の崩くずれた穴から、とある邸内に入り込み、下女につまみ出されそうになったところを教師(苦沙弥先生)に拾われ、住み込む。
登場人物
吾輩(主人公の猫)珍野家で飼われている雄猫。本編の語り手。「吾輩」は一人称であり、彼自身に名前はない。人間の生態を鋭く観察したり、猫ながら古今東西の文芸に通じており哲学的な思索にふけったりする。人間の内心を読むこともできる。
珍野 苦沙弥(ちんの くしゃみ)
猫「吾輩」の飼い主で、文明中学校の英語教師。妻と3人の娘がいる。偏屈な性格で、胃が弱く、ノイローゼ気味である(漱石自身がモデルとされる)。あばた面で、くちひげをたくわえる。その顔は今戸焼のタヌキとも評される。頭髪は長さ二寸くらい、左で分け、右端をちょっとはね返らせる。吸うタバコは朝日。酒は、元来飲めず、平生なら猪口で2杯。なお胃弱で健康に気を遣うあまり、毎食後にはタカジアスターゼを飲み、また時には鍼灸術を受け悲鳴を上げたり按腹もみ療治を受け悶絶したりとかなりの苦労人でもある。
御三(おさん)
珍野家の下女。名は清という。主人公の猫「吾輩」を好いていない。
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』吾輩は猫である
夏目漱石
夏目 漱石(なつめ そうせき、1867年2月9日〈慶応3年1月5日〉 - 1916年〈大正5年〉12月9日)は、日本の教師・小説家・評論家・英文学者・俳人。本名は夏目 金之助(なつめ きんのすけ)。俳号は愚陀仏。明治末期から大正初期にかけて活躍し、今日通用する言文一致の現代書き言葉を作った近代日本文学の文豪の一人。
代表作は『吾輩は猫である』『吾輩は猫である』『三四郎』『それから』『こゝろ』『明暗』など。明治の文豪として日本の千円紙幣の肖像にもなった。
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』夏目漱石
当サイト と らくらく読書プレーヤー について
当サイトは名作文学小説を当サイト独自開発のWebアプリ 読書プレーヤー(らくらく読書プレーヤー) を使ってご利用のウェブブラウザ上で手軽に読書できるサイトです。
ご利用のPC、スマホ、タブレット端末 等のウェブブラウザ上で
当サイト独自開発のWebアプリ らくらく読書プレーヤー
( *動作にはJavaScriptを有効にする必要有り )により
名作文学小説(青空文庫等で公開されている著作権が消滅した作品)を
文字のスクロール表示
テキストアドベンチャーやビジュアルノベルゲームのように各行の各文字を 1文字ずつ流れるよう に表示する機能。

上記は芥川龍之介の羅生門の1ページ目から2ページ目までの 1文字ずつ縦書き(タテ方向文字スクロール)表示 の例(GIF動画)
行ごとの終わりを意味する下向きの三角形のマーク
 が表示されているときにプレーヤーの画面上でクリックまたはタップすると次の行の表示に移ります。
が表示されているときにプレーヤーの画面上でクリックまたはタップすると次の行の表示に移ります。(上の画像(gif動画)のように自動的に次の行に進むわけではありません。1行毎にクリックしながら読み進めていき、現在ページの最終行の場合にクリックすると次のページに画面の表示が切り替わります。 *前のページに戻る機能 もあります。 )
縦書き(タテ方向への文字スクロール表示)、横書き(ヨコ方向への文字スクロール)表示の切り替え
以下は芥川龍之介の羅生門の1ページ目から2ページ目までの 1文字ずつ表示(ヨコ方向) に切り替えた場合の例(GIF動画)
(らくらく読書プレーヤーの設定画面から 縦書き(タテ方向表示) と 横書き(ヨコ方向表示) をそれぞれ切り替えることができます。)
同じページに表示される全ての漢字に ふりがな(ルビ) を表示可能 (全ルビ表示)
以下は芥川龍之介の羅生門の1ページ目で 全ての漢字にふりがな(ルビ) を表示した場合の例(画像)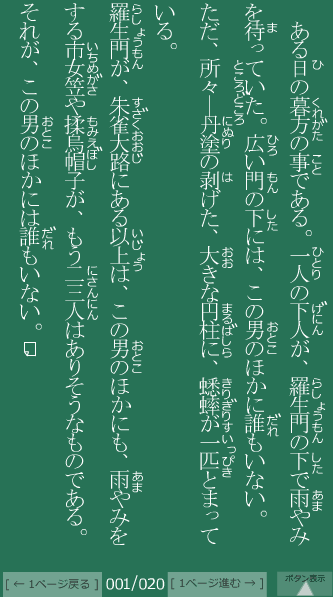
(らくらく読書プレーヤーの設定画面で ルビ(ふりがな)の表示方法 を切り替えることができます。)
最後に開いたページ番号を各作品(小説)別に自動的にブラウザに記録(保存)されるので次回以降、続きのページから読み始めることができる
などの機能を使って読書や漢字が苦手な方でも簡単にすらすらと読むことができます。
通常の紙媒体や電子書籍の小説の場合、1ページあたりの文字数が多すぎて読む気をなくしてしまう
(読書プレーヤーでは各行を1行ずつ、1文字単位のスクロール表示が可能)、
漢字の読み方(ふりがな<ルビ>)を忘れてしまって、そのたびに前のページに戻らないといけない などの理由で
読書に苦手意識のある方におすすめです。
また文字の表示方法として1文字単位のスクロール表示だけではなく
クリックまたはタップするごとに1行単位で表示するモード や 通常の小説のように1度に1ページ分の全ての文字を表示するモード
への変更(設定画面から変更可)もできます。
以下は芥川龍之介の羅生門の1ページ目から2ページ目までの 1行ずつ表示(全ての漢字にルビを表示) の例(GIF動画)
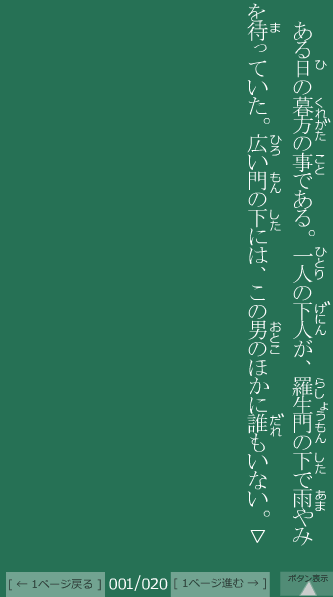
以下は 芥川龍之介の羅生門 のページで実際にスマートフォンのブラウザ上でらくらく読書プレーヤーが起動・表示されている様子のスクリーンショット画像です。タイトルバナー(以下の場合 らくらく読書 羅生門 芥川龍之介 という文字が表示されているバナー画像)の直下の部分で起動されます。(読書プレーヤーの 読み込み・起動 が完了するまでにはご利用のネットの回線速度や使用機種の処理速度等で変化し数秒~数十秒程度かかりますので起動が完了するまでしばらくお待ちください。)
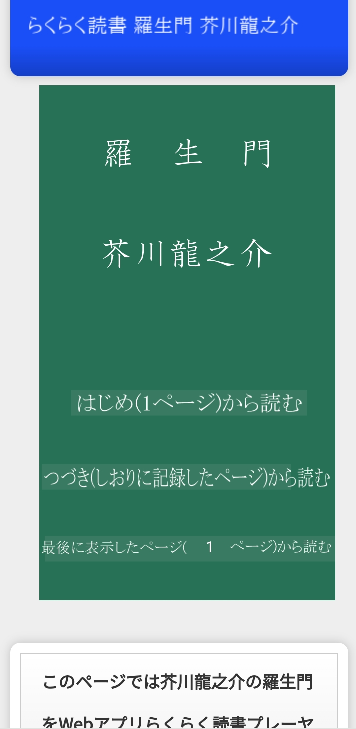
読書プレーヤー(ノベルプレーヤー) の操作方法の詳細 は らくらく読書プレーヤーの使い方(説明) からご覧いただけます。
*なお当サイトの読書プレーヤーの動作には JavaScript(ジャバスクリプト) を有効にする必要があります。
(動作しない場合はご利用の各ブラウザの設定画面で有効にしてください。)